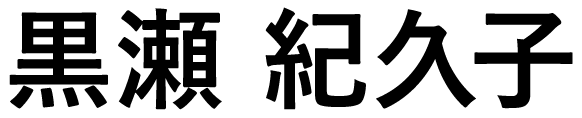50年を振り返ると、それは「闘い」だった。 まるで迷路をさまよっているようなこの道のりにはいつも闘いがあった。 何と闘っていたのか。 それは紛れもなく自分自身とであった。 自らの能力と、自らの精神と、自らの体力と、等々。 闘いは 果てしなく続いた。 それは時を追ってその姿を変えていったが、私にとって闘いである事はいつも変わらなかった。 それでも私を前に進ませたものがある。 それは2つあった。
1つは芸術のもたらす究極の美だった。 その姿は簡単には現れない。 そこには様々な闘いと忍耐と努力と幸運が必要だった。 彷徨っている闇のような迷路の中で、果実が熟すようにその時が来ると、美は突然現れる。 音が、音楽がこの世を離れ、渋い光を放ちながら舞う。 そこには何世紀も経た作曲家たちの姿も透けて見える。 それまでの闘いが報われる 瞬間だ。 それまでの悶絶は一瞬にして消え去る。 それはまるで、音楽の女神サンタ・チェチリアが 勝利の冠を私に差し出しているようだった。 その美に酔い、芸術の道に感謝する時だった。
そして次の瞬間からまた闘いが始まる。 垣間見た美に力を得、再び迷路を前に進む。
2つ目は「可能性」だった。
能力の限界、体力の限界は見えない。 いつも私はこの限界に対して不安を抱き、不信に苛まれ、にもかかわらず 同時に抱いていた希望とのせめぎ合いに悶えていた。 それでも迷路を進むことをやめなかったのは、無意識のうちに私の中に可能性を信じる部分がどこかにあったからだと思う。 それは何の根拠もない盲目的なものであったが、可能性を信じる事は私を大胆にさせ、楽観的にさえさせるものであった。 これがなかったら、私は50年もの間をやってこれなかったかもしれない。 自らの能力や体力の限界に対する不信を究極まで追い詰めることなく、どこかで可能性にすり替えていたのかもしれない。
50年は節目だ。 ここを通過すると、このすり替えはもう通用しないかもしれない。 なぜなら、老いがもたらす確かな限界が迫っているのを実感するからだ。
ここからが誤魔化しのきかない本来の闘いなのかもしれない。
だから、50年は特別なのだ。